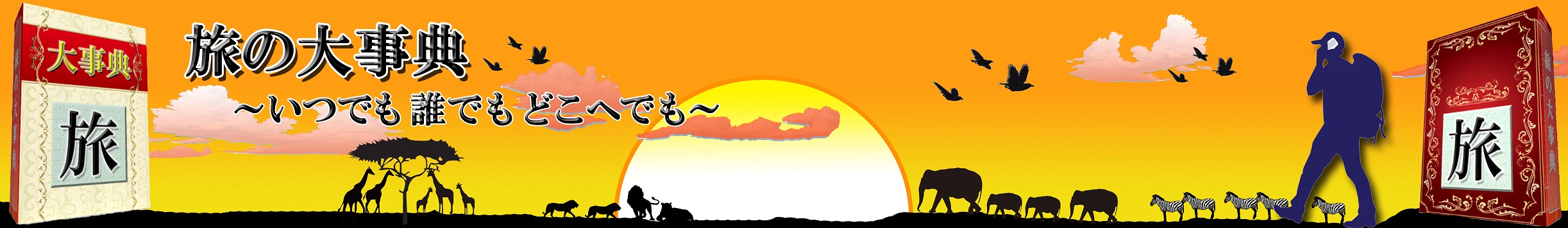ラリベラは巨大な岩をくり抜いて造られた教会群で、地面に突如現れる十字の教会があまりにも有名です。陸路で行くとかなり大変ですが、こちらのページでは陸路と空路両方の行き方をご紹介します(^^)
「ラリベラ」徹底ガイド:目次
1・拠点の街・最寄り空港・宿泊・通貨
2・空港から市内への移動
2-1:タクシーや配車アプリで行く
2-2:ミニバスで行く
2-3:空港送迎で行く
3・エチオピア観光の強い味方「ETT」
4・エチオピアン・タイムとエチオピア暦
5・ラリベラへのアクセス
5-1:飛行機で行く
5-2:バスで行く
6・ラリベラ
6-1:概要
6-2:聖ギオルギス教会(聖ジョージ教会)
6-3:第2グループ
6-3:第3グループ
7・世界の変わった外観の教会
8・コメント欄
9・観光の基本情報
グーグルマップを多用しているので通信環境の良い状態でご覧ください。マップの画面が黒くなっていたり、前後の文脈と合ってないなと感じたときは、ページを更新してみてくださいm(_ _)m
拠点の街はアジスアベバ。エチオピアの首都で、名前には「新しい花」という意味があります。アフリカ連合の本部などが置かれていて「アフリカの政治的な首都」とも呼ばれています。人口は約330万人。
最寄りの空港はアジスアベバのボレ国際空港。最新の就航路線はこちら。格安航空券はこちらです。
宿はこちら。宿泊したい範囲に拡大縮小したら、上の灰色の部分から日付などを選択。「Search」を押していただくと「Agoda」の検索結果に飛びますε=ε=ヽ(*・ω・)ノ
通貨はブル(通貨コード:ETB、記号:Br)で、補助通貨は「サンチーム(C)」。1ブル=100サンチームで、本日のレートはこちら。
空港から市内への移動

photo by:Vob08
空港は市内中心部から南東に約6km離れています。市内への移動方法は、タクシー、配車アプリ、ミニバス、空港送迎の4つです。

photo by:David
タクシーは2種類あり、青い車体が個人タクシーで、黄色い車体が空港タクシーです。空港タクシーは定額制で、行き先のホテルによって金額が決まっているため安心です(^^) 個人タクシーは特にメリットが無いので普通は使いません。安宿が多く集まるのは「ビアッサ地区」です。
■タクシー
・所要時間:15~30分
・料金:800~1200ブル
配車アプリは「Ride(ライド)」や「Feres(フェレス)」が使われており、タクシーより少し安くなります。
空港を出て、大通りに向かってまっすぐ歩くとガソリンスタンドが出てきます。そこがミニバス乗り場になっていて、青と白の車体が目印です。大きな荷物があると、もう1人分の料金を求められる可能性が高いです。

photo by:Ryan Kilpatrick
車体を見ても行き先はわかりませんので、周囲の人に「ビアッサ?」と聞いてみてください。料金は20~50ブルです。
空港送迎は色々あります。詳細は画像のリンクからご覧ください。
エチオピア観光は「ダナキル砂漠&ダロール火山&エルタ・アレ火山」「ラリベラ」「ムルシ族をはじめとした少数民族ツアー」の3つが定番の行き先です。これらのツアー手配や、個別のバスチケット、飛行機チケットなどを全て手配してくれる強い味方がETTこと「Ethio Travel And Tours」です。
ツアー手配すると、宿からバスターミナルへの無料送迎や、移動先の町の手頃な宿の予約なども合わせて行ってくれます。日本人観光客も基本的にETTを使うので、逆にそれ以外のツアー会社の情報を探すのが難しいほどです。
特別な理由が無い限り、エチオピア観光はETTにまかせていれば大丈夫です。予約や質問は公式HPから可能です。上記の地図の場所にはショッピングモールがありまして、ETTのオフィスは5Fにあります。
バスや飛行機のチケットを購入する際に注意しなくてはいけないのが「エチオピアン・タイム」の存在です。これは「エチオピア独自のタイムルール」で1日が「日の出=午前6時」から始まります。すなわち「本来は午前6時のとき、時計は午前0時を示している」ということです。
では、例えば「早朝4時発のバス」はどのように表記されるのでしょうか?「午前6時が、午前0時の表示」ですから、「午前4時は、6時間戻して午後10時の表示」ということになります。

実際にバスチケットを購入すると発車時間を「(午後)10:00」と記入されるのですが、これはエチオピアン・タイムであり、インターナショナルタイムの「午前4:00」ということです(^^;) 慣れるまではややこしいですが、とりあえず「アナログ時計もデジタル時計も6時間戻って表示されている」ということです。

特に厄介なのは南部の町です。少数民族の町や村ばかりになり、そもそもチケットが発行されなかったりするので、口頭で伝えられた時間に対し「エチオピアンタイムなのか、インターナショナルタイムなのか」を常に確認しないといけません。さらに、エチオピアには独自の「エチオピア暦」があり、1年が13ヶ月あるため、日付についても注意が必要です。
…すごい国ですよね(^^;)
ラリベラへのアクセス

photo by:Sm105
ラリベラの町から南西に約11km離れた場所に空港があります。タクシーがありますが、ラリベラの宿に送迎を頼んでおくのがオススメです(^^)
■タクシー
・所要時間:20~30分
・料金:500~800ブル
エチオピアは治安の面から夜行バスが禁止されています。つまり「日中しか走行できない」ため、アジスアベバからラリベラのような遠距離になると、直接行くことが不可能で、必ず途中の大きめな街で一泊することになります。「ラリベラ行き」の場合は、通常「デセ(Dessie)」という町で1泊し、翌日ラリベラへ向かいます。
■アジスアベバ→デセ
・早朝5時頃発
・所要時間:8~10時間
・料金:800~1500ブル
■デセ→ラリベラ
・早朝6時頃発
・所要時間:5~7時間
・料金:600~1000ブル
アジスアベバの長距離バスは、市内中心部の「マスカル・スクエア」周辺から出ます。「長距離バスターミナル」という統合された形ではなく、「スカイバス」や「サラムバス」など、各バス会社のオフィスから出発する形です。
バスチケットは前日までに購入するのが望ましいです。上記のバス会社のオフィスに直接行くほか、アジスアベバ最古のホテルとして知られる「Taitu ホテル」でもチケットを購入できます。
■Taitu ホテル
ただし、2025年末の段階で、アジスアベバとラリベラ間の「アムハラ州(デセもある)」は、政府軍と武装勢力の間で散発的な衝突や治安悪化が報告されています。バス移動中も検問が多く、通行止めや予期せぬトラブルが発生するリスクがあります。外務省の海外安全情報で「レベル3:渡航中止勧告」が出ているエリアも含まれるため、当分は飛行機での移動を選択してくださいm(_ _)m
ラリベラの町は元々「ロハ」と呼ばれていました。1162年にゲブレ・マスケルという王が誕生したのですが、彼が生まれたとき周囲に蜂が群がりました。人々は彼を「蜂に選ばれし者」を意味する「ラリベラ」とよび、いつしか町の名前もラリベラになったそうです。
ラリベラ王は、岩を削って11の教会をつくらせました。これが「ラリベラの岩窟教会群」として世界遺産に登録されていて、エチオピアにおいては「アクスム」に次ぐ聖地となっています。

教会群は大きく3つのエリアに分かれています。北の5つを「第1グループ」、南東の5つを「第2グループ」とよび、南西に「聖ギオルギス教会」が独立しています。
個人でも行けますが、町でガイドを雇うこともできます。ラリベラは実は標高3000m以上の高地にあり、教会はさらに高所に登らなくてはいけないため結構体力がいります。ロバに乗って行くことも出来るので、ご自身の体力に合わせて選んでみてください。
客引きはかなり多いですが、貧しいエチオピアにおいては貴重な収入源なので、仕方ないと思います。ぜひ交渉も楽しんでみてください(^^)
■ラリベラの岩窟教会群
・6~12時/13~18時
・料金:50USドル
一枚岩を掘りあげて造った十字の教会で、ラリベラの象徴敵な存在です。掘られている部分は縦・横・深さ全て約12mあります(,,゚Д゚)

聖ギオルギスは「ドラゴン退治」の伝説を持つ聖人で、キリスト教を嫌うローマ皇帝のディオクレティアヌス帝によって殉教死させられてしまいました。その後、ラリベラの王が他の10の教会を建て終わった頃、枕元に聖ギオルギスが現れて、彼のための教会を造るように言われ、この教会を造ったと言われています。

11の教会群の中で最も保存状態が良く、内部の壁には聖書の場面が色鮮やかに描かれています。クリスマスには約5万人のキリスト教徒が訪れるそうですΣ(゚∀゚ノ)ノ 内部はこちら。画面をグルッと回して周囲を見てみてください。
こちらは「聖救世主教会(マドハネ・アレム聖堂)」。世界最大級の岩窟聖堂で、縦が33m、横が22m、深さが11m、面積は800平方mにもなります。周囲には32本の柱がありギリシャ神殿のようなフォルムになっています。

ラリベラの教会群の中では最古と考えられていて、内部は「聖なる隠れ家」「秘密の聖地」という感じです(^^) 内部はこちら。
続いてこちらは「マリア教会」です。白いローグをまとった人がたくさん写っています。
てっきりイスラムのアバヤを着た女性かと思ってしまいますが、ここはキリスト教のエチオピア正教会です。画面を左に回してアップにしていただくと、多くは男性であることが分かります。内部はこちら。
他には、ラリベラ王の墓が残るとされる「ゴルゴタ教会」や「聖処女教会」などがあります。「ゴルゴダ」といえば、エルサレムの「ゴルゴダの丘」ですよね。実はラリベラは「第2のエルサレム」として建設されました。
■ゴルゴタ教会
上記のとおり、中東や地中海世界の影響を強く受けていたエチオピアでは、古くからキリスト教が伝わっていました。信者たちは聖地エルサレムへの巡礼を望みましたが、6世紀以降エルサレムはイスラム勢力が支配していたので、行くことができませんでした。
そこでラリベラ王が「第2のエルサレム」建設をかかげ、約24年の歳月をかけて教会群を造り上げました。そのため随所にエルサレムの地名などがつけられているというわけなんです。エルサレムの歴史については「エルサレム②歴史の基礎知識」をご覧ください。
こちらは王族の礼拝堂だったと言われる「聖エマニュエル教会」です。内部はこちら。
そのほか、刑務所として使われていた「聖メルコレウス教会」や、王宮だったとされる「聖ガブリエル・ラファエル聖堂」など、規模の大きな建物が残されています。
■聖ガブリエル・ラファエル聖堂
以上になります。エチオピアに残る「第2のエルサレム」。ぜひ行ってみてください(^^)
日本語で予約出来る現地ツアーもあります。詳細はこちらからご覧ください。
|
■ハットルグリムス教会(アイスランド) |
|
|---|---|
 |
アイスランドの首都レイキャビクにあるロケットのような形の教会です。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■カルパティア地方の木造教会群(ウクライナ・ポーランド) |
|

photo by:Elke Wetzig (Elya) |
16の木造教会が世界遺産に登録されています。どれもこれも、おとぎ話に出てくる建物のようです。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■サグラダファミリア(スペイン) |
|
 |
言わずとしれた「未完の大聖堂」で、アントニオ・ガウディが生涯をかけて建設に取り組みました。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■グルントヴィークス教会(デンマーク) |
|
 |
1940年に完成した教会で「表現様式」という珍しい様式で建てられています。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■ラ・アルタグラシア聖堂(ドミニカ共和国) |
|
 |
モダン建築の独特なデザインと、ステンドグラスに彩られた幻想的な内部が有名です。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■トロムスダーレン教会(ノルウェー) |
|
 |
トロムソは北欧北部の「ラップランド」と呼ばれるエリアにあり、シャチをスノーケリングで見られるスゴイ場所です。その街のランドマークの教会で「北極大聖堂」とも呼ばれています。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■ヘルシンキの教会(フィンランド) |
|
 |
ヘルシンキは知る人ぞ知るアーティスティックな都市で、教会や礼拝堂も面白いデザインのものが多くあります。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■ブラジリア大聖堂(ブラジル) |
|
 |
ブラジリアの象徴ともいえる建築物で、内部も教会とは思えない近未来なデザインになっています。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■リオデジャネイロ大聖堂(ブラジル) |
|
 |
1976年に造られたモダン建築の教会で、リオデジャネイロのランドマークの1つです。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■ポルトの教会(ポルトガル) |
|
 |
ポルトは「アズレージョ」と呼ばれるブルータイルが名産で、教会や駅などが唯一無二の外観になっています。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■モルドヴィア地方の教会群(ルーマニア) |
|
 |
ルーマニア北部のスチャバ県に点在する8つのルーマニア正教会を指します。一般的な教会と違って建物の外壁部分にフレスコ画が描かれているのが特徴です。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■キジ島の木造教会(ロシア) |
|
 |
キジ島は木造の巨大建築物であるプレオブラジェンスカヤ教会などが有名で、それらの教会は世界遺産に登録されています。詳細は下記からご覧ください。 |
世界には他にも魅力的な教会や修道院がたくさんあります。興味のある方は「世界のすごい教会・修道院総特集②」をご覧ください。当サイトで取り上げている教会や修道院の中から、特にすごい155ヶ所をテーマ別にご紹介しています(^^)
| 航空便例 | ・日本-ドバイ(約11時間)
・ドバイ-アジスアベバ(約4時間) |
|---|---|
| ベストシーズン | 10月~4月(乾季) |
| 治安 | 海外安全情報 エチオピア |
| ガイドブック | 東アフリカのガイドブック |
| ビザ | ビザ取得が必要 |
| パスポート残存期間 | 申請時6ヶ月以上 |
| 時差 | -6時間(サマータイム無し) |
| チップ | 基本的には不要 |
| 日本への電話 | 00(国際識別番号)と81(日本の国番号)をつけて、市外局番(東京:03など)や携帯電話の090などの最初の0を取る。
例)03-9999-9999へかける場合 |
| 現地で使えるアムハラ語 | ①おはよう。
男:ウンデムン アッダルク
②こんにちは。
③こんばんは。
④ありがとう。
⑤さようなら。
⑥はい・いいえ |
| 電圧とプラグ | 220V
|
| 通貨とレート | ブル(通貨コード:ETB、記号:Br)で、補助通貨は「サンチーム(C)」。1ブル=100サンチーム。
|
| 日本大使館 | ・HP |
| エチオピアの絶景一覧 |
アイコンをクリックすると「名前/写真/ガイド記事へのリンク」が表示され、リンクをクリックすると別ウィンドウで記事が開きます。グーグルマップを使用してリンクを貼っているため「リダイレクトの警告」が表示されるかもしれませんが、全て確実に当サイト内のリンク(http://tabinodaiziten.com~)なのでご安心ください。また、地図にアイコンが表示されていないときはページを更新してみてくださいm(_ _)m
■赤のアイコン
個別のガイド記事です。
■その他の色のアイコン
大都市など周辺に見どころが多い場所や、1つの国の中で同系統の見どころがあるとき、複数の見どころを1つの記事に集約していて、それらが同じ色のアイコンになっています。青、緑、紫…など様々な色がありますが、まとまりを分かりやすくしているだけで、色ごとに意味が異なるわけではありません。