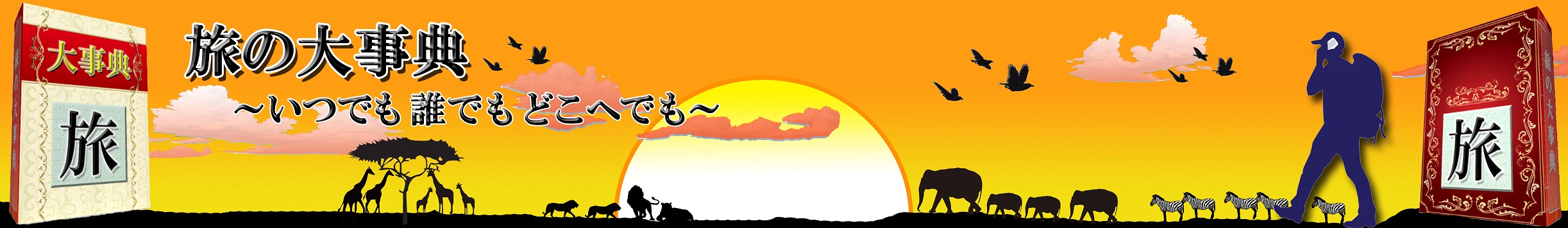麻豆代天府(マードウダイ・ティエンフー)は台湾屈指の道教寺院で、佐藤健寿さんの写真集「奇界遺産」で取り上げられて日本でも知られるようになりました。巨大な龍の胎内には天国と地獄が表現されていて、ちょっとしたお化け屋敷のようになっています(^^)
「麻豆代天府」徹底ガイド:目次
1・拠点の街・最寄り空港・宿泊・通貨
2・台南空港から市内への移動
3・台北から台南への移動
3-1:高速鉄道で行く
3-2:その他の移動方法
4・高雄から台南への移動
4-1:高速鉄道で行く
4-2:普通の電車で行く
4-3:バスで行く
5・台中から台南への移動
5-1:高速鉄道で行く
5-2:その他の移動方法
6・麻豆代天府へのアクセス
6-1:概要
6-2:新営駅から直通バスで行く
6-3:台南駅からバスを乗り継ぎ行く
6-4:隆田駅からタクシーで行く
6-5:隆田駅からバスと徒歩で行く
7・麻豆代天府
8・世界のドラゴンスポット
9・コメント欄
10・観光の基本情報
グーグルマップを多用しているので通信環境の良い状態でご覧ください。マップの画面が黒くなっていたり、前後の文脈と合ってないなと感じたときは、ページを更新してみてくださいm(_ _)m
拠点の街は台南市。台湾で最も早くに開けた地域の1つで、元々「台湾」という言葉は「台南地域」にのみ使われる言葉でした。現在は台湾6大直轄地の1つです。人口は約190万人。
最寄りの空港は台南空港(TNN)。最新の就航路線はこちら。格安航空券はこちらです。
宿はこちら。宿泊したい範囲に拡大縮小したら、上の灰色の部分から日付などを選択。「Search」を押していただくと「Agoda」の検索結果に飛びますε=ε=ヽ(*・ω・)ノ
通貨は台湾元(通貨コード:TWD、記号:NT$)で、読み方は「Yuan」。補助通貨は「角(Mao)」と「分(Fen)」ですが「分」は使われていません。1元=10角=100分で、本日のレートはこちら。
台南空港から市内への移動

photo by:Asacyan
空港は市内中心部から南に約6km離れています。市内への移動方法はバスかタクシーです。空港の地上交通のページはこちら。

「5番」のバスが空港と市内をつないでいます。青で囲んだのが空港で、緑が台南駅です。
・6~22時頃まで運行
・30~60分に1本程度
・所要時間:40~60分
・料金:18元
・公式HP
・メーター制
・所要時間:20~30分
・料金:300~400元
・赤:台北駅
・青:南港駅
台北市には高速鉄道の駅が2つあります。台南市の到着駅はどちらも「高鉄台南站」です。「高鉄台南站」は台南市中心部から少し離れていて、電車で台南駅まで行く必要があります。
・所要時間:約1時間半
・料金:約1300元
■高鉄台南站

photo by:Asacyan
・各駅、急行、特急などあり
・特急:約3時間半
・料金:約750元
■高速バス
・24時間体制で複数の会社が運行
・所要時間:3時間半~5時間
・料金:400~600元
高雄から台南への移動

photo by:Tai
新左営駅から高鉄台南站へ高速鉄道がつながっています。ただ、上記のとおり「高鉄台南站」は台南駅へ乗り継がないと行けないので、普通の鉄道を使う方が簡単です。
・所要時間:10~15分
・料金:135元~

photo by:Foxy1219
高雄駅から台南駅へ直通列車が出ています。
・20分に1本程度
・各駅:約1時間
・急行:約45分
・特急:約35分
・料金:74元~
高雄空港から台南バスターミナル行きの直通バスが出ています。
■台南バスターミナル

photo by:台南賴哥
・所要時間:1時間半~2時間
・料金:300元
台中から台南への移動

photo by:vegafish
高鉄台中駅から高鉄台南站へ高速鉄道がつながっています。
・所要時間:35~45分
・料金:630元~
・各駅、急行、特急などあり
・特急:約1時間45分
・料金:約360元
■高速バス
・24時間体制で複数の会社が運行
・所要時間:2時間半~
・料金:250~500元
・赤:麻豆代天府
・青:新営駅
・青:隆田駅
・紫:台南駅
麻豆代天府は、とても微妙な場所にあります( ̄▽ ̄;) すぐ近くに、路線バスの「黄幹線(Yellow Main Line)」の「五王廟前」というバス停があるので、公共交通機関で行く場合はここを目指します。「新営駅」からは直通バスがあり、「台南駅」からは1回バスを乗り換えます。電車で「隆田駅」へ行くと、タクシーで行ける距離になりまして、バスで600mほど離れたバス停へ行くこともできます。それでは、それぞれご説明します。
台湾北部の「新営駅」前のバスターミナルから、「黄幹線」のバスに乗ると「五王廟(麻豆代天府)前」まで一本で行けます。
・所要時間:約50分
・料金:18~36元
こちらは「在来線の台南駅」で、上記の「高鉄台南駅」とは場所が全く違うので注意してください。ここから下記のバスに乗り「麻豆転運站」で下車します。
・「7505番」「橘13番」のバス
・所要時間:40~60分
・料金:18元~
「麻豆転運站」は「麻豆地区の乗り換えバスターミナル」という感じです(^^) 上記の「黄幹線」がつながっているので、「五王廟(麻豆代天府)前」まで一本で行けます。
■バス
・所要時間:約10分
・料金:18元
ただ、「黄幹線」は本数が多いわけではないため、時間帯によっては乗り継ぎが悪い可能性があります。もう近いので、そのときはタクシーを使っても良いと思いますが、帰りをバスにするなら時刻表をしっかり確認しておいてください。
■タクシー
・所要時間:約5分
・料金:100~150元
台南駅などから電車で「隆田駅(Longtian Station)」へ行き、そこからタクシーに乗る方法です。
■タクシー
・所要時間:15分
・料金:250~500元
麻豆代天府の周辺に「流し」のタクシーはいないので、そのタクシーに1時間待機してもらったり、迎えの時間を指定して来てもらったり、またはUberを呼ぶなど、「帰りの足の確保」を忘れないようにしてください。
上記のとおり「五王廟(麻豆代天府)前」のバス停で「黄幹線」に乗ることができるので、「新営駅」へ行くことや、「麻豆転運站」を経由して「台南駅」へ行くことは可能です。
「隆田駅」から「橘10」「橘10-1」などのバスに乗って「麻豆公所」で下車し、麻豆代天府まで約10分歩きます。ε=ε=ヽ(*・ω・)ノ ただ、本数が少ないのであまり実用的ではありません。やはり「帰りの時刻表」をしっかり確認してください。
■バス
・所要時間:約30分
・料金:18~26元
台湾には道教信仰がありまして、中でも「王爺(おうや)」という神様を祀る「王爺信仰」は台湾で広く見られます。麻豆代天府は明代末期の1662年に建立された王爺信仰の本廟で、日本の感覚では「寺院」と捉えると分かりやすいです。
「李・池・吳・朱・范」という五王も祀っているので「五王廟」とも呼ばれます。建造当初は「保寧宮」という名前でしたが損傷がひどくなり、別な場所に「保安宮」として移転されました。その後、1955年に「保寧宮」があった場所に「麻豆代天府」が造られ現在にいたります。
敷地は約1万坪もあり、三大殿や觀音寶殿などが建てられています。画面をグルっと回して周囲を見てみてください。3年に一度大きな祭りが開かれているので、そこに合わせて行くのもオススメです(^^) 敷地内に入ると、まず現れるのが「觀音寶殿」です。

photo by:lienyuan lee
色鮮やかなデザインとユニークな形が特徴で、中には観音様がまつられています。
そして最大の見どころが境内の裏にある「五彩觀光巨龍」です(,,゚Д゚)

長さ約76m、高さ約7m、1979年に約1億元を投じて建てられましたΣ(゚∀゚ノ)ノ

photo by:林振宇
てっきり口から入るのかと思いますが、口は出口になっていて、まずは地獄の入口からスタートします。入場料は40元です。
地獄では「閻魔様に刑罰を決められてから刑が執行されるまで」が、お化け屋敷のような感じで表現されています。そして、一度地獄を出てから天国へと進んでいきます。
こちらも40元の入場料がかかります。天国はどこもホンワカしています(*´ω`*) そして、出口がここというわけです。
龍はやっぱりカッコいいですね。インスタ映えポイントなので、たくさん良い写真が撮れます。

以上になります。台湾が誇る道教の聖地「麻豆代天府」。ぜひ行ってみてください(^^)
台湾は日本語で予約出来る現地ツアーも多くあります。詳細はこちらからご覧ください。
|
■竜の橋(スロヴェニア) |
|
|---|---|
 |
首都のリュブリャナにある橋で、合計4体の竜が人々を見守っています。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■ドラゴン・ディセンデンツ・ミュージアム(タイ) |
|
 |
スパンブリーにある「中国の歴史をテーマとした博物館」です。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■ワット・サームプラーン(タイ) |
|
 |
ナコーンパトム県にある寺院で、とある僧侶が夢の中で建設を促されて造りました。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■ワット・バーン・タム(タイ) |
|
 |
「戦場にかける橋」で知られるカンチャナブリーにあります。 詳細は下記からご覧ください。 |
|
■龍虎塔(台湾) |
|
 |
高雄市にある塔で、台湾を代表するパワースポットとして知られています。こちらは「ドラゴン(竜)」というより「龍」という感じですね。東洋っぽくて良いです(^^) 詳細は下記からご覧ください。 |
|
■ドラッヘン橋(ドイツ) |
|
 |
ルール地方の「ヘルテン」という町にあります。「ヨーロッパのRPG」的なドラゴンで、かなり巨大なので見ごたえがあります。詳細は下記からご覧ください。 |
|
■ドラゴンブリッジ(ベトナム) |
|
 |
2013年にビーチリゾートのダナンに造られた橋です。なんと…火を吹きますΣ(゚∀゚ノ)ノ 詳細は下記からご覧ください。 |
| 航空便例 | 日本-台南(約4時間) |
|---|---|
| ベストシーズン | 10月~4月 |
| 治安 | 海外安全情報 台湾 |
| ガイドブック | 台湾のガイドブック |
| ビザ | 2025年10月から入国カード(Arrival Card)が完全オンライン化され、紙のカードは廃止。旅行者は到着3日前までに申請が必要。また、到着日の翌日深夜0時から起算して90泊91日以内の滞在はビザ不要。 |
| パスポート残存期間 | 滞在日数以上 |
| 時差 | -1時間(サマータイム無し) |
| チップ | 基本的には不要 |
| 日本への電話 | 002(国際識別番号)と81(日本の国番号)をつけて、市外局番(東京:03など)や携帯電話の090などの最初の0を取る。
例)03-9999-9999へかける場合 |
| 現地で使える中国語 | ①おはよう。
早安.(ザオアン)
②こんにちは。
③こんばんは。
④ありがとう。
⑤さようなら。
⑥はい・いいえ。
⑦~へ行きたい。
⑧これがほしいです。
⑨これはいくらですか?
⑩値下げしてくれませんか? |
| 電圧とプラグ | 110V
|
| 通貨とレート | 台湾元(通貨コード:TWD、記号:NT$)で、読み方は「Yuan」。補助通貨は「角(Mao)」と「分(Fen)」だが「分」は使われていない。1元=10角=100分
|
| 日本大使館 | HP(正常な国交が無いため大使館は無く、「日本台湾交流協会」が同じ役割を担っています) |
| 台湾の絶景一覧 |
アイコンをクリックすると「名前/写真/ガイド記事へのリンク」が表示され、リンクをクリックすると別ウィンドウで記事が開きます。グーグルマップを使用してリンクを貼っているため「リダイレクトの警告」が表示されるかもしれませんが、全て確実に当サイト内のリンク(http://tabinodaiziten.com~)なのでご安心ください。また、地図にアイコンが表示されていないときはページを更新してみてくださいm(_ _)m
■赤のアイコン
個別のガイド記事です。
■その他の色のアイコン
1つの国に同系統の場所が複数あるときや、多くの見どころが集中している大都市などは、1つのページで複数の場所をご紹介していて、それらが同じ色になっています。青、緑、紫…など様々な色がありますが、まとまりを分かりやすくしているだけで、色ごとに意味が異なるわけではありません。